妊娠・出産を控えて迎える産休中。
いざ時間ができても
「 何をして過ごせばいいの? 」と
悩む女性は多いですよね。
出産後は赤ちゃん中心の生活になり、
自分のためにまとまった時間をとることが難しくなります。
だからこそ、
産休中の過ごし方はとても大切。
この記事では、
「 産休中やってよかったこと 」 を中心に、
先輩ママの声やおすすめの過ごし方、
産休中に役立つ準備リスト5選を紹介します。
これから産休・育休に入る方の参考になるよう、体験談を交えながらまとめました。
ぜひ最後までお読みください🍀
産休と育休の違いを知ろう!
私自身も妊娠するまで産休と育休の違いが理解できていませんでした。
それぞれの違いについて、
まとめてみたのでご覧ください!
1. 制度の根拠法律が違う
- 産休(産前産後休業)
労働基準法で定められている制度。妊娠・出産する女性労働者が対象。 - 育休(育児休業)
育児・介護休業法で定められている制度。男女問わず取得可能。
2. 取得できる期間の違い
- 産休
- 出産予定日の 6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前) から取得できる
- 出産の翌日から 8週間は就業禁止(医師が認めれば6週間後から復帰可)
- 育休
- 出産後、子どもが 1歳になるまで が原則
- 保育園に入れないなど条件を満たすと 最長2歳まで延長可能
3. 対象者の違い
- 産休
→ 出産する女性本人だけが対象。 - 育休
→ 男女問わず取得できる。父親も育休を取れる。
4. お金の違い
- 産休中
→ 給料の代わりに「出産手当金(健康保険から支給)」がもらえる。
金額はおおよそ「給料の約2/3」。 - 育休中
→ 雇用保険から「育児休業給付金」が支給される。
金額は休業前の給与の 67%(最初の6か月間)→ 50%(それ以降)。
(2025年8月現在)
5. 目的の違い
- 産休
母体の健康と出産に備えること、産後の回復のため。 - 育休
子どもを育てるため、親子の時間を確保するため。
分かりやすい比較表
| 項目 | 産休 | 育休 |
|---|---|---|
| 法律根拠 | 労働基準法 | 育児・介護休業法 |
| 取得対象 | 出産する女性本人 | 男女問わず |
| 期間 | 出産予定日6週間前〜産後8週間 | 出産後〜子ども1歳(最長2歳) |
| 給付金 | 出産手当金(健康保険から) | 育児休業給付金(雇用保険から) |
| 主な目的 | 出産準備・母体の回復 | 子育て・親子の時間確保 |
先輩ママ・パパの声
- 産休は本当に体を休める時間、育休は赤ちゃんと向き合う時間だと実感しました
- パパも育休を取ってくれたので、産後のサポートが手厚くて助かりました
- 制度を知らなかったら損していたと思う。早めに調べて準備しておくのが大事!
産休中にやってよかったこと5選
産休に入ると、仕事から離れてホッとできる一方で「 時間をどう使うか 」に迷う方が多いです。
- やっと自由時間ができた!
→ だらだら過ごして後悔する人も。
- やりたいことが多すぎる!
→ 無理をして体調を崩す人も。
大切なのは
「 今しかできないこと 」を見極めること。
妊娠中の体調を考えながら、無理なく自分に合った過ごし方を選びましょう。
産休中は「 自分のため 」と
「 赤ちゃんのため 」のバランスを大切に🌟
1. 睡眠と体調管理を最優先に
出産後は「 まとまった睡眠がとれない 」とよく言われます。
実際に産後すぐは夜中の授乳や赤ちゃんのお世話で寝不足が続きます。
産休中は無理に予定を詰め込まず、
「 昼寝もOK 」くらいの気持ちで体を休める時間を大切にしましょう。
2. 出産・育児の情報収集
SNSや本、ママ友の体験談から
「 産後のリアルな生活 」を知るのもおすすめ。
- 出産準備品のリスト確認
- 産後の手続き(児童手当、医療費助成、保育園申し込みなど)
- 授乳・沐浴などの基礎知識
情報を先に知っておくことで、
産後に慌てずに済みます。
3. 家事・育児の分担を夫婦で話し合う
産後は「 こんなはずじゃなかった 」と
夫婦間でギクシャクすることも。
産休中におすすめなのが、パートナーと家事・育児の役割を具体的に話し合うことです。
- 掃除や洗濯の担当をどうするか
- 夜中の授乳やオムツ替えを分担するか
- 実家やファミリーサポートの利用はどうするか
事前に話し合っておくだけで、
産後のストレスを大きく減らせます。
4. 趣味や資格の勉強にチャレンジ
「 子育てが始まると時間がなくなる 」と
聞いて産休中に資格の勉強や趣味に取り組む人も多いです。
- 語学の勉強(英語や韓国語)
- 家計管理やファイナンシャルプランナーの勉強
- ハンドメイドや料理のスキルアップ
出産後は「 自分だけの時間 」が激減するので、この時期に好きなことに没頭するのはとても有意義です。
5. 写真・日記で「妊娠中の記録」を残す
お腹が大きくなる過程やマタニティライフを写真や日記で残しておくと、後で見返したときにとても良い思い出になります。
また、体調や気持ちを日記に残すと産後の振り返りや次の妊娠の参考になりました。
産休中のタイムスケジュール例
「 何をすればいいか分からない 」という方に向けて、モデルとなる1日の過ごし方を紹介します。
- 8:00 起床・朝食
- 10:00 家事・買い物
(無理のない範囲で) - 12:00 昼食
- 13:00 昼寝・休憩
- 15:00 趣味や勉強の時間
- 17:00 散歩やストレッチ
- 19:00 夕食
- 21:00 入浴・リラックス
- 23:00 就寝
無理のないペースで
「 体を休めながら、自分の時間も楽しむ 」のがポイントです。
まとめ|貴重な時間を過ごそう
産休中は、
人生の中でも特別で貴重な時間です。
- 体を休めること
- 情報や準備を整えること
- パートナーと協力体制を築くこと
- 自分のための時間を楽しむこと
これらを意識するだけで、
産休・育休がより充実したものになります。

また出産に向けて、いつ陣痛が来るのか
分からないためマタニティタクシーに登録しました!
私が登録したマタニティタクシーはドライバーの方が助産師指導のマタニティ研修を受講し、破水等で車内を汚してもクリーニング代は不要とのことでした。
🌟事前に自宅や出産予定日、
病院などの情報を登録する必要があります。
お住いの地域によって違うと思うので、
一度マタニティタクシーについて
調べてみてください!
無理せず自分に合った過ごし方を見つけてください😌
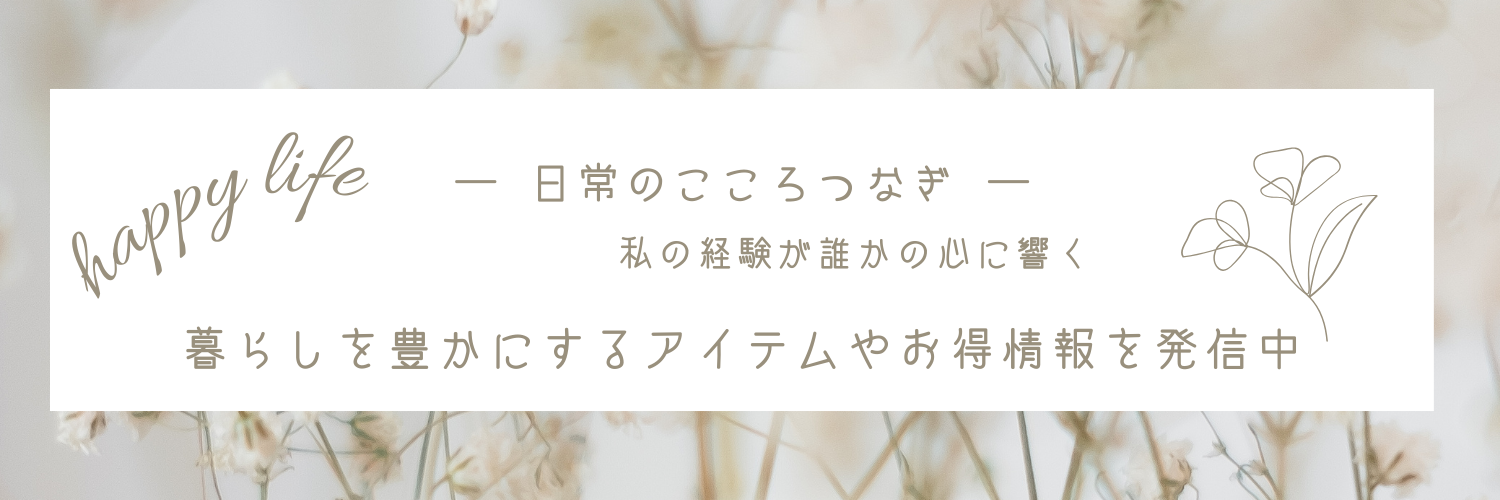
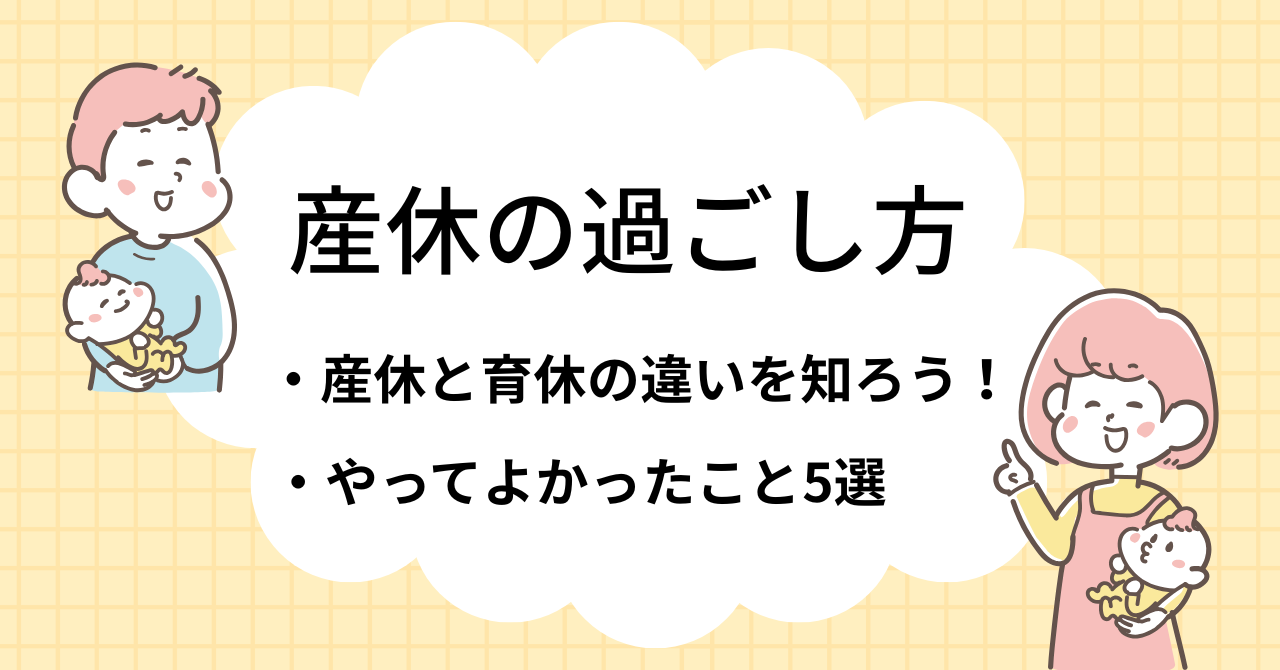
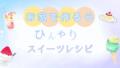
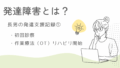
コメント