我が家の長男は1歳から保育園いきました。
保育園に行き始めると月歴に違いは
ありますが、クラスのお友だちと
言葉や行動を比べてしまう場面がありました。
そんな長男が
「 他の子とは違う? 」と思った経緯と、
受診したきっかけをお伝えしますので
最後までお読みください!
発達障害とは?
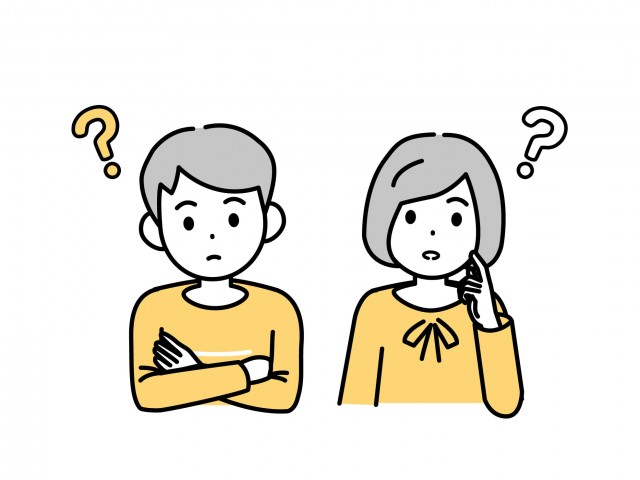
保育園や小学校の集団生活が始まると、
他の子どもと比べる機会が増える時期です。
このタイミングで、以下のような違和感に気づく保護者や先生が多いです。
よくある「気づき」のサイン
- 指示が通りにくい、集団行動が苦手
- コミュニケーションが一方的、または極端に少ない
- 手先が極端に不器用/運動が苦手
- 過敏・鈍感(音・光・触覚など)
- 興味の偏り、強いこだわり
- 感情のコントロールが難しい(癇癪、パニックなど)
発達障害の種類と特徴
- ASD(自閉スペクトラム症):対人関係・コミュニケーションの困難、こだわり
- ADHD(注意欠如・多動症):集中力の持続が困難、不注意・多動・衝動性
- LD(学習障害):読む・書く・計算など特定の分野に著しい困難
我が家の長男は3歳になっても
発音がはっきりせず、
話すことができませんでした。
話す言葉は自分が興味のあるものくらいで、
保育園であった出来事やお友達の
名前も言えませんでした。
受診に至った経緯について

3歳児検診では指示されたことはできず、
絵を見ても物の名前が言えませんでした。
保健師さんに「 家では言えてるかな?できているかな? 」と聞かれ、「 はっきりとは言えないけどわかってはいます。 」と答えた記憶があります。
年少の時、担任の先生に相談したところ、
発達については個人差があるし集団生活は
問題なく過ごせているとのことでした。
いつか話せるようになるだろう
と思っていましたが、
お友達とのトラブルがきっかけとなり、
予防接種のついでに病院へ相談しました。
そこから保育園を通じて市の発達相談を受け
小児科専門医を紹介してもらいました。
受診する前にできること
- 言葉の発達、運動能力、対人関係、
こだわりの強さなど、日常の様子を
丁寧に観察する。 - 「他の子と比べる」より、「その子自身のペースや変化」を見ることが大切です。
- 気になる言動、保育園での様子などを
メモに残しておくと、医師へ伝えやすいです。
療育・リハビリについて
初診では保育園の様子や家での生活、
気になることをたくさん聞かれました。
医師からの質問を答え点数をつける
問診の結果、自閉症の傾向がある
とのことでした。
これから親としてどうすればいいのか、
すごく不安な気持ちになったことを
覚えています。
ですが、息子が今後、
話せないことで辛い思いをしないためにも
できることから始めることにしました。
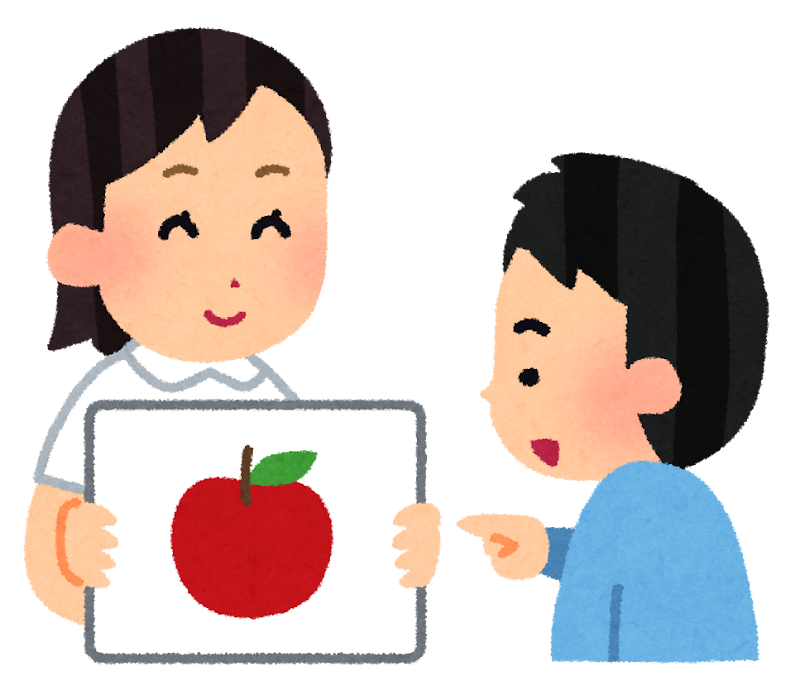
言語聴覚士(ST:Speech Therapist)
言語聴覚士は、言葉の理解・表出、コミュニケーション能力、聞く力などをサポートします。
- ことばの理解・表出、コミュニケーション能力を評価・訓練
- 食べる・飲み込むこと(嚥下)に関しても専門です。
- 絵カード、視覚支援、AAC(補助代替コミュニケーション)
作業療法士(OT:Occupational Therapist)
作業療法士は、日常生活動作、感覚の統合、身体の使い方などを支援します。
- 日常生活動作
(着替え、食事、トイレなど) - 手先の動き、体の使い方、感覚の調整
(感覚統合) - 注意力や身体の使い方(バランス・姿勢)の調整
息子は月に1回、
STとOTに通っています。
先生との相性もよく
40分間のリハビリは楽しいようです。
本人が楽しくできるリハビリが一番ですね😊
リハビリの内容は後日、書きたいと思います!
子どもとの関わり方

発達障害の有無にかかわらず、
「 その子の特性に合った関わり 」
がとても大切です。
焦らない・責めない
- 発達の特性は「その子の個性」であり、親の育て方のせいではありません。
- 「 この子が生きやすくなるために、今できるサポートを 」と考えましょう。
- 得意なこと・好きなことに目を向けて、自信を育てることが発達全体の支えになります。
情報を整理・信頼できる支援者を見つける
- 信頼できる支援者(保育士、心理士、医師など)とつながることが大きな支えになります。
- ネットの情報は玉石混交なので、医療機関や自治体の情報を中心に。
具体的な接し方の例:
- 安心できる環境を整える:予測しやすいスケジュール、過度な刺激を減らす
- 視覚的なサポートを使う:スケジュール表、イラスト、マークなど
- 具体的・短く伝える:「片付けて」ではなく「ブロックを箱に入れて」
- 否定よりも肯定を優先:「◯◯しないで」ではなく「◯◯しようね」
- 成功体験を積ませる:できたことを一緒に喜ぶ、小さな達成感を重ねる
「 困っているのは子ども自身 」
という視点で、責めずにサポートを。
早期発見・早期支援が、
子どもの可能性を広げます。
専門家に相談することは
親として不安だからこそできる前向きな一歩 です。
子どもの特性を理解し、成長の道筋に寄り添うことが大切だと思います。
多動や不注意に悩む親御さんも多いですが、
「気づき」は支援のスタートライン。
子どもがより生きやすくなるような
関わり方を、周囲と一緒に少しずつ
工夫して過ごしてみてください!
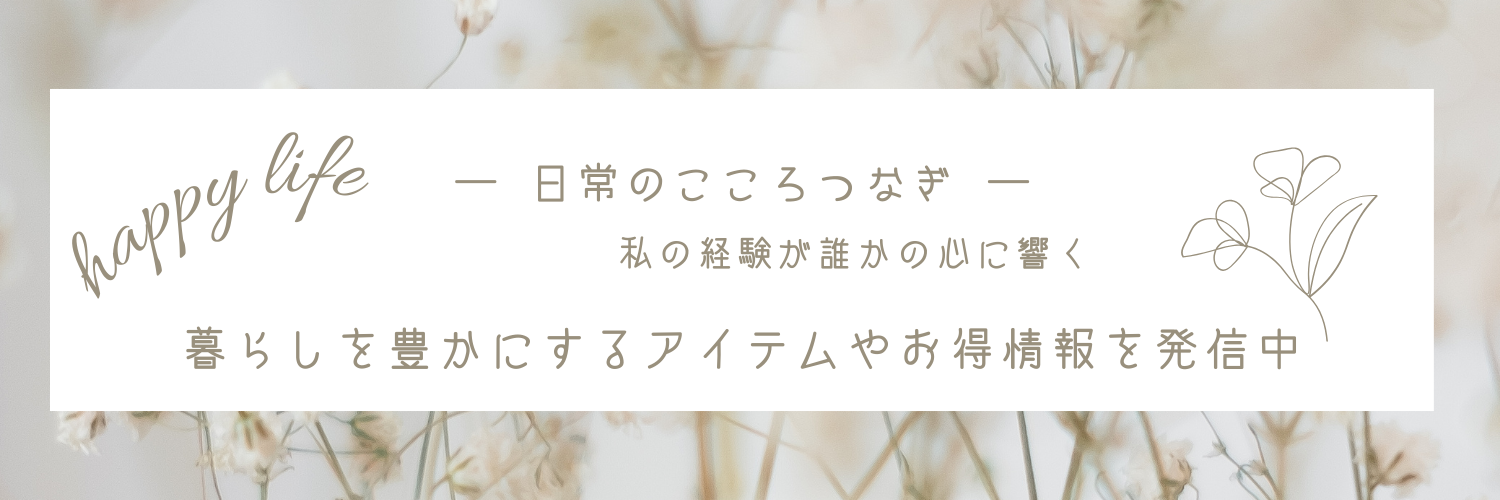



コメント