以前のブログで長男の発達について
投稿しました。
↓ こちらになります ↓

今回は長男の発達支援の記録として、
実際に通っているリハビリの内容や効果、
家庭で取り入れている工夫をまとめました。
これから療育を始める方や同じように悩んでいるご家庭の参考になれば幸いです。
受診に至った経緯について
前回のブログではサラッと書いてしまいましたが、今回は詳細にお伝えしたいと思います。
年少時の様子
・発音がうまくできない
・集中力が短い
・多動
・先生のお話が聞けない
ざっと思い浮かぶ様子はこんな感じでした。
保育園では大きなトラブルはなく
このまま年中さんになるんだなぁ
と思っていた年度末、
トラブルが発生しました🌀
お友だちとのトラブルは
会話がうまくできないことが事の発端でした。
「 何を言っているのか分からない!! 」
とお友だちに強く言われてしまい、
背中を噛まれ、リュックのファスナーに
付いていたお名前のタグを引きちぎられました。
担任の先生から報告を受け、
正直ショックだったし、
悲しかったことを覚えています。
親として悩んだこと
子どもに何かあったとき、
ママ自身が自分を責めませんか?
他の子と比べてしまい、
「 私の育て方が悪かったのではないか 」と。
私もたくさん自分を責めました。
妊娠中の過ごし方、食生活、産後の過ごし方、息子との過ごし方など、、、
ですが、悩んでも解決はしないし
息子にとって悲しい思いをさせないためにも
今できることをやっていこう!
と気持ちを切り替えて進むことにしました。
作業療法リハビリ(OT)の内容|R6.10.21~
作業療法では、
「 日常生活で必要な動作を練習すること 」
を目的にリハビリが行われます。
初回のOTリハは以下のような内容でした↓
1. 絵の中から指示されたものを答える
3歳児検診でやったような
はさみ・えんぴつ・車・くつ・コップなどの
絵カードを使いました。
「 はさみはどれ? 」から始まり、
「 紙を切るものはどれ? 」と
物を使う用途に質問を変えて答えていくものでした。
【 結果 】
物の名前や使い方は理解できていることがわかりました。
2. 大小の違いを理解する
絵カードを使い、
・ 小さいはさみはどっち?
・ 大きい車はどれ?
・ この絵のなかで一番大きいのはどれ?
というような質問に答えていくものでした。
【 結果 】
大小の違いはしっかり理解できていました。
3. 指示されたことをやってみる
絵カードは使わず実物の物を使いました。
① 積み木の上にはさみを置いてみて
② はさみの上に積み木を置いてみて
③ 車の近くに積み木を置いてみて
④ コップの中に積み木を入れてみて
⑤ 先生の手に犬の置物を置いてみて
など、さまざまな指示をやってみました。
【 結果 】
集中力が切れてきたのか多動が目立ち、
立ち上がることが増えましたが、
指示されたことはだいたいできていました。
できなかったことは
「 ③ 車の近くに積み木を置く 」でした。
長男は積み木を車の横に置きました。
4.言葉だけの理解
絵カードや物を使わず、
頭の中で考えて答える訓練でした。
① 車とりんご、大きいのはどっち?
→ くるま!
② 飛行機とみかん、乗ることができるのはどっち?
→ 飛行機!
③ 車と飛行機、大きいのはどっち?
→ 同じ!
④りんごと車、小さいのはどっち?
→ ん~、同じかな…
【 結果 】
集中力切れで答えるのに時間が掛かりました。
だいたい答えることができましたが、
言葉だけで考えることは苦手で
理解できていないことが分かりました。
OTリハを通して分かったこと
初回のOTリハを通して分かったことは、
物の名前、使い方は理解できているが、
目で見えないものは理解できていないことが分かりました。
家庭でできること
目からの情報と耳からの情報を一致させるための訓練が必要
と先生からアドバイスをもらいました。
私が家庭で取り入れたものは、
「 絵本を一緒に読む! 」
当たり前のように思う方もいらっしゃると思いますが、私の場合はワンオペ育児のため、なかなか一緒に読むことはできませんでした。
ただ読むのではなく、絵本の中に出てくる
・りんごを探してみて!
・食べられるものはどれ?
・乗れるものはどれ?
・この中で一番大きい or 小さいものはどれ?
・これってどうやって使うの?
など、
物語よりも絵本の中に出てくる物や大きさ、形、色に重点をおき質問して答えてもらうことを繰り返し行っています。
家庭で取り入れている工夫
リハビリだけでなく、
家庭でのサポートも大切です。
私たちが意識していることを紹介します。
- 小さな成功体験を積み重ねる
「 できた! 」をたくさん経験させることで、自己肯定感を育てる。 - 無理をさせない
疲れているときは無理に練習させず、休ませることも支援のひとつ。 - 兄弟や家族と一緒に楽しむ
遊びの中で自然にことばや動作を引き出すようにしています。
生活の一部として、小さな繰り返しを大きな成果につなげてサポートしています。
まとめ | 息子と共に成長する

リハビリは、
「 生きやすさ 」につながる大切な支援です。
長男の発達支援を通じて、
「 子どもの強みを伸ばす 」
という視点を学びました。
同じように悩んでいる方に伝えたいのは、
👉 一人で抱え込まなくて大丈夫
👉 小さな一歩の積み重ねが大きな成長につながる
ということです。
これからも、長男の成長を支えながら、日々の工夫や気づきを発信していけたらと思います。
言語のリハビリは年長になってから始めるという担当医の判断だったので、言語リハビリについてはまたブログにまとめたいと思います✨
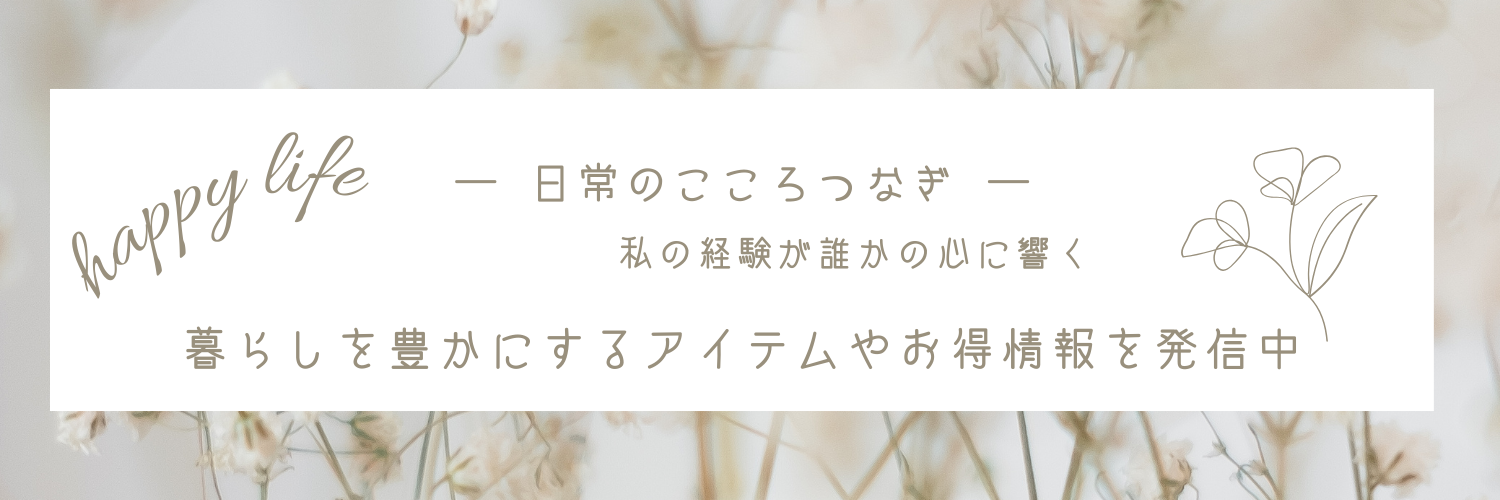
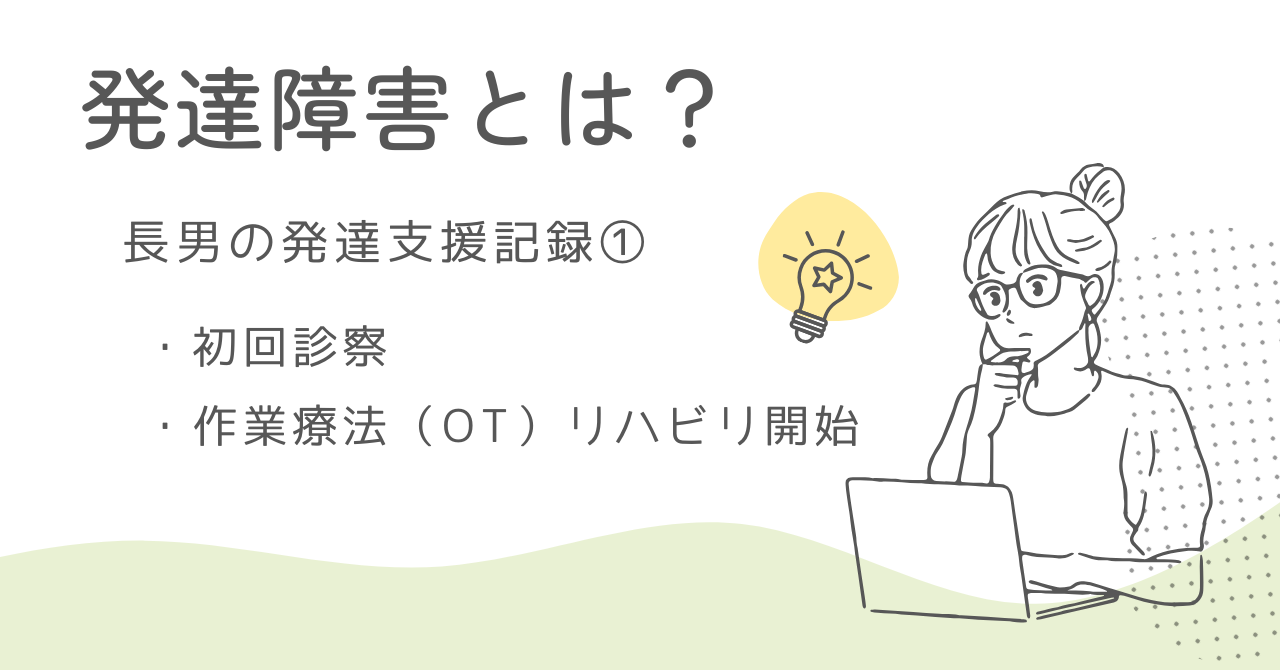
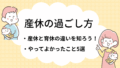
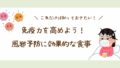
コメント